「結果を出す」ことと「実感を与える」こと。
どちらが重要かと問われれば結果と答えるが、どちらを優先するかと問われれば実感と答える。
頭は良くならない。幼児のうちはまだしも、小学校高学年あたりから急に頭が良くなることはない。賢さ、勘の良さと言い換えてもいい。
努力次第で多少の改善はできるだろうが、劇的に良くなることはない。そもそも頭の良し悪しが、努力によって身につけられる量に影響を与えているのだから。塾に行ってから成績が伸びた、なんてヤツはもともとそれなりに頭が良かったか、ものすごく成績が悪かったかのどっちかだ。
だから、全ての生徒の成績を上げることは難しい。いや、成績は上げられるが、本人や保護者が望むレベルまで上げることは難しい。
しかし、実感を与えることはそんなに難しくない。
俺は魔法が使える。どんな魔法かと言うと「生徒の口から正解を言わせる」魔法だ。
「問題です。ルート4を簡単にすると」
「4だからぁ…じゅうろ」
「ブー! なんでやねん。逆や逆」
「えっ、なに? 逆?」
「4を2乗するんやなくて、2乗して4になる数を考えんと」
「あ、そっか。えっと、プラスマイ」
「ブー! 『4の平方根』やったらプラスマイナスいるけどな~」
「え、じゃぁ…2?」
「そ。正解。じゃあ、ルート49だったら?」
「49だから…7!」
「うん、正解。ほしたら、ルート4分の1は?」
「ええっ、4分の1ぃ?」
「ちなみにルート4は2やったなぁ」
「ルート4が2だからぁ…え、2分の1?」
「2分の1かぁ…ファイナルアンサー?」
「ええっ? (しばし考えて)ファイナルアンサー」
「あ~あ。…正解(笑)。最後。マイナスルート81は?」
「9」
「ブブー。お前なぁ、最後やっつーのになんでまちが」
「ちがっ、マイナス9だ!」
「そうそうそう! OK? わかった? もう大丈夫?」
「(笑いながらうなずいて)大丈夫です」
「ちなみに、マイナスルート36だったら?」
「マイナス6」
「よし」
何のことはない。自分からは答えを言わず、正解が出てくるまで粘り強く聞くだけ。ヒントを色々出したり、質問の仕方を変えてみたり。要するに誘導尋問だよな。
ついでに言うと「わかった」の前に「わからない」と思わせるのもポイントだったりする。実は、上のやりとりの前に、こんなことを言ってる。
「学校じゃもう平方根はやってるよな」
「はい」
「じゃ、訊くで。-16の平方根は?」
「-16? えっと…-4」
「ほうほう、-4か。ちなみに-4を2乗すると何になる?」
「-16」
「なんでやねん。-4かける-4やで。正負の計算からやり直さなアカンか?」
「あっ、違う、16だ。あれ?」
「せやなぁ。-16にならんなぁ」
「え~、なんだろう…」
「おいおい、学校でやったことなのに、ハナからわかってないやんけ。ちなみに正解は『ナシ』や。だってそうやろ、2乗して負の数になるわけないやんか」
「あー、そっかー」
実は、これは教科書に書いてないこと。おそらく学校の授業でも触れてないこと。平方根は正の数を前提に展開していく。だから「平方根が無い」という選択肢が無い。わからなくて当たり前。
そうして「わかってない」と思わせてから「わかった」と思える状態に持って行く。そうすると、例えテストで間違えたとしても「塾でやったときはわかったのに」って思う。むしろ塾で出来たのに学校のテストで間違えたってのは望むところ。「復習せな」って言えるし。
で、無理繰り結論に持って行くと。
俺は塾で勉強を教えてるけど、それはサービス業だと思ってる。提供するのは満足感。教わって良かった、また教わりたいって思ってくれる様に頑張るだけ。

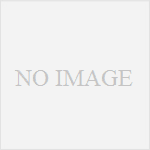
コメント