解釈は3通り。
A:6÷2(1+2)=6÷2×3=3×3=9
B:6÷2(1+2)=6÷6=1
C:6÷2(1+2)=6÷2+4=3+4=7
まずA。
最も優先順位の高いカッコを先に計算すると、6÷2(3)となる。
ここで2(3)を「ああ、×が省略されてるのね」と考えると、6÷2(3)=6÷2×3となり。
後は左から順に計算していって、9。
次にB。
演算子を外側から考えると、まず●÷■の形である。
(この考えを当然と思うには、演算のパラメータとなる「項」の認識が必要)
さすれば●=6、■=2(1+2)=2×3=6
最終的に6÷6=1
最後にC。
これはバカの一つ覚えみたいに「きたっ! 分配法則! 俺それ知ってる!」としか…。
まぁ、これを小学生への問題にしたのなら、正解は「問題が間違ってます」だろう。
中学生に対してa÷b(x+y)と出題したなら。
a/{b(x+y)}もしくはa/(bx+by)が正解。
ちゃんと分数表現をした場合、aが分子になっているという意味ね。
ちなみに。
2(1+2)=6は正しい。
故に気の利いたプログラムであれば、題名の解は単に「×」を補完したAパターンとなる。
加減乗除が二項演算であること、ひいては「項」とはなんぞや、ということが(言葉でうまく説明できなくても)理解できているかを問うには、いい問題かも知れない。

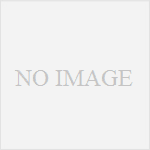
コメント
「1」だと思った。